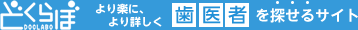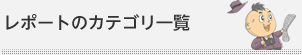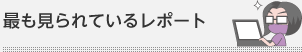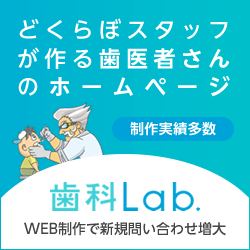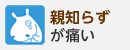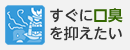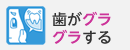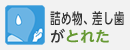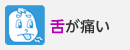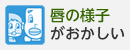そもそも味覚障害とは?分類について
味覚障害と聞いて、皆様はどのような症状を想像しますでしょうか? 『味覚』というものは、人間が生きて上で非常に重要な感覚と言うことができます。そんな味覚に障害が生じると聞くと、とてもたいそうな病気を想像してしまいそうですが、一言に味覚障害といってもその種類は様々です。加齢にあわせて緩やかに進行する生理的な(特に異常ではないという意味)味覚障害から、特定の原因によって生じる特殊な味覚障害まで。まずは、「味覚障害」について、症状の特徴別にその大まかな分類をご説明させて頂きます!
味覚障害と一言に言ってもその障害の出方によってタイプは様々存在しますこれから紹介する4つの味覚障害がそれぞれ独立して発症するのではなく、幾つかのタイプが複合して発症するケースも存在します。
味覚障害の分類①:味を薄く感じてしまうタイプの味覚障害
味覚障害の中でも最も一般的と言えるものが、
- 味覚減退
と呼ばれるタイプのものです。
「同じ味の濃さのものを口にしても、以前と比べて薄味に感じてしまう」といったケースにあてはまるのが『味覚減退』です。味覚減退の中にも、その程度の差によって様々な症例が存在しますが、「味を全く感じなくなってしまう。といった特に症状の悪いケースでは『無味症』という名称で呼ばれることもあります。
味覚障害の分類②:口に何も入れてないのに味を感じてしまうタイプの味覚障害
何も食べていないのにうっすらと ”味” を感じる気がするケースは、
- 自発性異常味覚
と呼ばれる味覚障害があてはまるかもしれません。これは、自発的、つまり ”何もしないでも勝手に” 存在しない味覚を感じてしまうタイプの味覚障害を指します。先程ご紹介した味覚減退と比べ、比較的症例の少ないタイプの味覚障害とも言えます。
味覚障害の分類③:本来とは違う味を感じてしまうタイプの味覚障害
味を薄く感じてしまう「味覚減退」、何も食べていないのに味を感じてしまう「自発性異常味覚」。異なる2つのタイプの味覚障害をご紹介してきましたが、続いては本来とは違う味を感じてしまうタイプの味覚障害です。
「味のないティシュペーパーなのに何故か甘みを感じてしまう!」症例がとても少なく、発症する年齢も限られるようですが、このようなケースには、
- 異味症
と呼ばれる味覚障害があてはまるかもしれません。ティシュペーパーなどならば生命を脅かす危険度は低いですが、小石やプラスチックといったものに味を感じてしまうケースではすぐに適切な対応が必要であると言えます。
味覚障害の分類④:特定の味だけを感じなくなってしまうタイプの味覚障害
最後にご紹介するのは、
- 解離性味覚障害
と呼ばれる味覚障害です。
「他の食事は以前と変わらないのに、甘いものだけ感じなくなってしまった!」ある特定の味覚が ”解離(カイリ)” つまり切り離されてしまうという訳です。消えてしまう味覚の種類は様々ですが、中でも『甘み』だけを感じなくなってしまう症例が最も多いようです。
味覚障害がカラダに与える影響
放置しておくとどうなる?
味覚障害を放置した場合に、すぐさま他の大きな病気が発症してしまうことは、あまり考えにくいとされています。しかし、味覚障害によって味覚に ”偏り” が生じてしまうと、その変化に応じて普段の食生活の内容に同じく ”偏り” が生じてしまうケースは多く存在します!
食生活の偏りはどんな病気にも良い影響を与えず、また、重大な大病の原因に繋がることも考えられます。味覚障害が生じた場合は、食生活が極端な偏りの原因となってしまわないよう、味覚の改善にしっかりと向き合うようにしましょう!
味覚障害の特徴は?診断方法について
骨折などの外傷や特定のウイルスによって発症するインフルエンザなどと異なり、「味覚」という人それぞれの感覚に異常が生じてしまう味覚障害は、その診断がとても難しいとされています。とはいっても、どんな病気も適切な治療を開始するためには、事前の正確な診断がとても重要です。ここからは、味覚障害の検査/診断法について、現在医療の現場で用いられているものを簡単にご紹介致します。
味覚障害の検査/診断①:問診
味覚障害の診断に限らずどんな病気でも重要になっているのが、
- 問診
です。病院に来る方はそれぞれに異なる理由が持っておられます。「なぜ検査を受けようと思ったのか?」というシンプルな質問に対する答えからでも、知識のある医療スタッフは様々な治療に必要な様々な情報を得ることが出来ます。
しっかりと正確に伝えること
人間の感覚に異常をきたしてしまう味覚障害では、患者自信の言葉による症状の情報がとりわけ重要となってきます。「異常を感じだしたのはいつからか?」「ある特定の味だけに異常を感じるのではないか?」「味覚障害とは異なるその他の全身疾患を有していない?」「現在服用している薬剤はあるか?」等々、、味覚障害に関する特殊な検査を始める前に、これらの細かな質問を医師から受けるかと思いますが、その後の治療を大きく左右してゆくことになりますので、その際はしっかりと正直な情報を伝えるよう心がけましょう!
味覚障害の検査/診断②:視診
「舌の色に異常はないか?」「舌を含めた口の中全体が極度に乾燥していないか?」などなど、舌を目で視る
- 視診
は、先程の問診と合わせて、味覚障害の診断において最低限必要な検査法と言うことが出来ます。
味覚障害では、”舌(=べろ)を目で視る” ことも大変重要な検査となります。後程くわしくご説明致しますが、味覚障害の中には火傷や炎症などの舌に生じる、その他の病変に伴って生じるものも存在します。
味覚障害の検査/診断③:味覚検査
『問診』『視診』とどんな病気の診断にも必須なステップについてご紹介してきましたが、ここからは、味覚障害の検査/診断に用いられる ”特殊な” 検査/診断法についてご紹介致します。
ろ紙ディスク法
ろ紙ディスク法とは、甘み/辛み/酸味/苦みなどの異なる味をつけた小さな用紙(ろ紙)を、舌の特定の部位に乗せ、それらの感じ方を記録する味覚の検査法です。この『ろ紙ディスク法』は、大がかりな特殊機材を必要としませんので、多くの医療機関の味覚障害治療に用いられている検査法と言えます。
ろ紙ディスク法を用いると、「異常を感じる味覚は決まっていないか?」「舌特定の部分でだけで障害が生じていないか?」といった点に対する情報を得ることが可能となります。
電気味覚検査
『電気味覚検査』と呼ばれる味覚検査は、電流を流した小さな電極を舌の特定部位に当てることで、味を感じる神経の反応を観察するものです。
先程ご紹介したろ紙ディスク法と比べると、特殊な機材を必要とする分やや大掛かりな検査とも言えますが、流す電流の量もごくごく微量ですので患者の負担も非常に少ないため、ろ紙ディスク法と並んで、味覚障害の診断で広く用いられている検査法です。『電気味覚検査』では、障害が生じている部位を特定出来るほか、電極に流す電流の大きさを調節することで「どのくらい味覚が損なわれているのか?」といった異常の ”程度” を判断するために貴重な情報を得ることが出来ます。
見た目の変化について
先程も少しご紹介したように、味覚障害は「舌の火傷(ヤケド)」といった味覚障害そのものとは異なるその他疾患に付随して生じるケースがあります。そういったタイプの味覚障害では、舌のが普段よりも赤っぽくなっていたりと、舌の炎症症状を見た目として確認出来ることもございます。
口腔乾燥症について
また、後ほど詳しく触れてゆきますが、『口腔乾燥症』というキーワードも味覚障害を語る上で外せない重要ワードなのです。口腔乾燥とは、その名の通り「口の中が過度に乾燥している状態」を指します。
口の中が乾燥しすぎてしまうと味覚に異常をきたしてしまうケースが存在するのですが、口腔乾燥症は分泌される唾液(つば)の量以外に、口の中の ”色味” によってもその程度を確認することが可能です。一般的に、口の中が極度に乾燥してしまうと ”舌を含めた口全体が白っぽく変化する” ことが知られています。
同時に起こりやすいカラダの症状は?
先程少し触れた『口腔乾燥症』を始め、味覚障害はその他の疾患に付随して生じるケースが多く存在します。この後の見出しから説明する ”味覚障害の原因” でも細かく触れますが、以下の疾患ではそれ本体に併せて『味覚障害』が生じてしまう可能性があることが知られています。味覚障害を併発しやすいその他の疾患についてご説明いたします。
シェーグレン症候群
口の中の乾燥や目の乾燥を主な症状とする自己免疫性の疾患です。
糖尿病
血糖値のコントロールに不備が生じてしまう有名な全身疾患ですね。糖尿病では唾液の分泌が減少することがあり、それが味覚障害に関係していると考えられています。
消化器系疾患
バランス良く”味” を感じるためには、舌の組織が健全な状態であることが非常に重要です。小腸などの消化器系の臓器に何か疾患が生じていると、舌の組織が不健全な状態に陥ってしまうケースがあります。そうなってしまうと、程度の差はあれど、味覚に障害や変化が生じてしまうことが知られています。
妊娠
妊娠は全く持って病気ではありませんが、”通常の状態とは異なる”という点で普段とは異なる身体の異変が生じることが知られています。味覚についても同じく、妊娠している女性では味覚の障害や変化が生じるケースが多いです。
味覚障害が起こる原因について
『味覚障害』について、その症状別の分類と検査/診断法についてご紹介してきましたが、ここからはその原因についてご説明致します!ここまでで触れてきたように、単に『味覚障害』といってもその症状は様々であり、1つの決まった症状だけではなく複数が組み合わさって発症することも稀ではありません。したがって、それらの原因も「これだけ!」といったようにハッキリと特定することは非常に難しいと考えられています。以下に、これまでの症例や研究によってその関連性が示唆されている ”味覚障害の原因” についてご紹介してゆきます。
味覚障害の原因①:亜鉛不足
『亜鉛』という物質が、身体にとって非常に重要な栄養素であることをご存知でしょうか?味覚障害は、この亜鉛の不足によって生じてしまうことが広く知られているのです。亜鉛は、身体の中に存在する元素の中で『鉄分』と同程度に重要とされています。健全な身体の維持には、身体を構成している「細胞」が上手く細胞分裂をしてゆくことが必要と言えます。「代謝促進して健康を手に入れる!」といったキャッチコピーを耳にすることがありますが、『代謝(新陳代謝)』という言葉は、『細胞の分裂』と捉えることが可能です(厳密には異なる用語なのですが、、) 。
亜鉛不足が味覚異常を引き起こす理由
亜鉛という物質は、細胞が活発に分裂する際に非常に重要な役割をなすことが知られています。舌には、味を感じるための『味蕾』という組織が数多く存在しており、味蕾には小さな小さな『味細胞』が数多く詰まっています。『味細胞』とは、その名の通り味覚を感じるための細胞であり、この細胞の量や質が変化することにより味覚障害が生じてしまうと考えられているのです。舌の『味蕾』に含まれる『味細胞』。味細胞は、その重要な役割とともに、その分裂頻度が非常に活発であることも重要な特徴の1つです。先程触れた『亜鉛』は、細胞が ”分裂” する上で非常に重要な役割をはたす物質です。その亜鉛が不足してしまうことで、味細胞の分裂(=代謝)に変化が生じる。この変化が原因で味覚障害が生じてしまう、という訳なのです。
味覚障害の原因②:口腔乾燥症
ここまででも何度か触れてきたように、口の中が過度に乾燥してしまう『口腔乾燥症』は味覚障害と密接な関係を持っています。人が食事をとり、その『味』を感じるためには、口にいれた味物質(食物)が、先程も出てきた『味蕾』へ流れ込むことが必要となります。味蕾に流れ込んだ味物質は、味蕾を構成している『味細胞』の表面と接することで、人間は味覚を感じることが出来るという訳です。味物質が味蕾へスムーズに流れ込むには、口の中の唾液(つば)が潤滑油のような役割をすると考えられています。唾液の分泌が減少する『口腔乾燥症』では、味の”素”となる味物質が十分に味蕾に入りこむことが出来ずに、その結果、味を感じづらくなるなどの味覚障害を状してしまうことがあるようです。
口腔乾燥症として名の挙がる疾患
味覚障害を引き起こしてしまう『口腔乾燥症』を生じる疾患は様々あることが知られています。ここまででも少し紹介した『シェーグレン症候群』や『糖尿病』、後ほど触れる『薬剤性唾液分泌障害』などが、口腔乾燥症としてよく名前の挙がる疾患です。
関連記事:口腔乾燥症って何?唾液現象の弊害と、原因から導く4つの治療法について。
味覚障害の原因③:ストレス
ストレスによっても味覚に異常(変化)が生じることが知られています!過度なストレスや、いわゆる『うつ病』などのメンタル面で生じる疾患では、程度の差はあれども自律神経のバランスが崩れてしまう傾向にあります。先程から何度か出てきている「口腔乾燥」は、自律神経の乱れからも生じることが知られています。
- ストレスが蓄積する
- 自律神経が乱れる
- 唾液が少なくなって口が乾燥する
- 味覚に障害(変化)が生じる
というメカニズムです。
味覚障害の原因④:薬の副作用
ここまで何度も紹介してきた『口腔乾燥症』。服用する薬剤の副作用によっても生じることが知られています!薬の副作用により唾液が減少してしまうものを『薬物性唾液分泌障害』と呼ぶのですが、これを引き起こす原因薬剤は、大きく以下の2種類に分類されると言われております。
1、神経に作用する薬
唾液の分泌を減少させ、その結果味覚障害の引き金となってしまう副作用を持つ薬剤の代表が、『抗うつ薬』などの神経に作用する薬剤です。
自律神経に作用して目的の効果を得る薬剤では、その副作用として唾液を作り出す臓器(唾液腺)の活動が鈍くなってしまうことが知られています。このような副作用が出る薬剤としては、抗うつ薬以外にも『抗不安薬』、『抗コリン薬』、『抗ヒスタミン薬』などが存在します!これら薬剤を服用している際には、軽度~中程度の味覚障害が生じることが多いので、実際に服用する際には副作用についてもしっかり情報を得るように心がけましょう。
2、身体の水分バランスを調整する薬
味覚障害を引き起こす可能性のある薬剤の2つめのタイプは、『高圧剤』などに代表される、身体の中の水分バランスを調整する機能を持つ薬剤です。
高血圧の治療に用いられる高圧薬の中には、細胞への水分の流入が少なくなってしまうことが知られています。唾液を作り出すためには、水分が必要不可欠です。したがって、高圧薬の服用によって、唾液を造る細胞へ十分な量の水分が行き届かずに、結果として唾液の分泌が減ってしまい味覚の障害に繋がってしまう!という訳です。
味覚障害の原因⑤:加齢
「年をとる」ことは、病気ではなく極めて自然な現象ですが、加齢によっても味覚障害が出てしまうケースがあります!
人間に限らず地球上に生きる全ての生物は、年を重ねるごとにその機能が徐々に低下してゆく傾向があるのがご存知の通り。舌の表面に存在する『味蕾』の数も高齢になると減少してゆきますし、唾液を造る臓器の働きも加齢に伴い低下してゆくことが知られています。
味覚障害の原因⑥:脳の異常
最後にご紹介する味覚障害の原因は、『脳』に関する異常です。脳の異常と聞くと、味覚障害がとても大きな大病と思えてしまいますが、脳の異常が原因となる味覚障害は極めて症例が少ない部類に入りますのでご安心を。しかし、実際に ”その人が脳障害になるかどうか?” ということは、単純な確率論だけで語ることは難しい部分もありますので、これまでに紹介してきた原因が見当たらないのに、急に味覚に障害を感じた場合は、念のためにすぐに医療機関を受診することをおすすめ致します。
味覚障害の治療・予防方法
ここからは、治療/予防法についてご説明してゆきます。
そもそも何科を受診すれば良いの?
これまでご紹介してきたように、単に『味覚障害』と言っても、その症状や原因は非常にバリエーションに富んでいるのが現実です。先程触れた「脳障害が原因の味覚障害」といった稀なケースではそもそも味覚障害よりも優先して治療すべき状況になることも考えられますし、その治療の場は各症例によって異なってくることが少なくありません。
適切な治療を始める前には、それぞれの味覚障害の原因をしっかり突き止めなければなりません。味覚障害が疑われる場合は、まずは一般の歯科医院を受診し簡単な検査を受け、原因追及が難しい場合や治療が複雑になる場合は専門の大学病院などを紹介してもらうことが望ましいです。逆に、軽度の味覚障害などでは、街の一般歯科でも診断/治療を完結してしまえるケースも多くありますので、繰り返しますが、味覚障害が心配になった場合は、
早めに最寄りの歯科医院を受診するよう心がけましょう!
どんな治療法がある?
味覚障害の治療は、その原因に合わせて様々存在します。以下に、味覚障害の原因別にその治療について簡単にご紹介致します。
薬剤の副作用による味覚障害の治療
味覚障害 ”だけ” を改善するためには、極端な話、使用している薬剤の服用をストップすることが考えられます。しかし、そもそも薬剤を服用している時点で、その理由となる ”他の病変” が存在しています。服用を止めると生命を脅かしてしまうケースも考えられますので、個人の判断により使用薬剤の服用をスットップしてしまうのは絶対にNGです!
どうしても味覚障害が気になってしまう場合は、かかりつけの医療スタッフにしっかり意思表示をすることが重要です。病状によっては、服用薬剤を減量することが可能なケースもありますので、『味覚障害』と『服用薬剤に関するその他疾患』の治療の優先度のバランスについてしっかりと医師からの説明を受けるよう心がけましょう。
亜鉛の不足による味覚障害の治療
亜鉛不足によって生じる味覚障害では、不足分の亜鉛を補うことが一番の治療となります!亜鉛が多く含まれる食事を摂ることも非常に有効ですし、亜鉛欠乏に対して処方される『亜鉛製剤』を服用することも多く選択されます。
治療と言うよりも ”予防” という観点ですが、亜鉛欠乏によって味覚障害は生じてしまわないように、普段からの食生活には十分注意しましょう!
<亜鉛欠乏に陥り易い食生活>
- 加工食品に偏りすぎた食生活
- 野菜を省いた食生活
- 清涼飲料水の飲み過ぎ
<亜鉛を多く含む食品>
- ごま
- 肉製品
- 海草類
- 貝類
加齢などの自然な口腔乾燥症による味覚障害の治療
加齢で唾液分泌が減少してしまった場合の味覚障害の治療では、唾液腺マッサージなど唾液の分泌を自然に促す対応が選択されます。顎の下にある唾液を作り出す臓器を軽くマッサージすることで、一時的に唾液の分泌が増加することが知られています。また、こまめに水分を摂取して口腔内の乾燥を防ぐことも有効とされています。
なお、この2つの対応法
- マッサージ
- 水分摂取
は、その他の味覚障害に対しても大なり小なり有効と考えておりますので、妊娠時などで軽度の味覚障害を感じている方には非常におすすめですよ!
治療にかかる日数は?
治療法が様々存在することから、味覚障害の治療にかかる日数は一概には断言することは出来ません。しかし、亜鉛欠乏による味覚障害に限れば、不足分の亜鉛を摂取し始めてから、
約2〜3ヶ月
で味覚が改善されてくることが知られています。
治療にかかる費用は?
治療にかかる費用についても、はっきりとした目安は存在致しません。ただ、味覚障害に関する簡単な相談については、一般の歯科医院にて保険内の虫歯診療と同程度の費用で行なってもらえますので、味覚障害が疑われる場合は、すぐにかかりつけの歯科医院を受診するよう心がけましょう!
まとめ 味覚障害と一緒におこりやすい病気や関連病について
これまで何度も出てきたキーワードですが、『口腔乾燥症』は味覚障害を語る上で欠かすことの出来ない重要な症状/疾患と言えます。口腔乾燥症は、タバコや食生活に関連する比較的 ”なり易い” タイプのものから、遺伝的な原因を有する ”特殊な” タイプの口腔乾燥症まで、その種類は様々存在します。口腔乾燥症についてだけまとめた書籍や専門のクリニックも存在しますので、気になる症状がある方は、是非とも『口腔乾燥症』について、深く情報を集めてみることをおすすめ致します。
最後に「味覚障害」について重要な点をおさらいしておきましょう。
<味覚障害の分類>
- 味覚減退
- 自発性異常味覚
- 異味症
- 解離性味覚障害
<味覚障害の診断方法>
- 問診
- ろ紙ディスク法
- 電気味覚検査
<味覚障害の原因>
- 亜鉛不足
- 口腔乾燥症
- ストレス
- 薬の副作用
<味覚障害の治療>
- 亜鉛を摂取する
- マッサージ
- 水分補給
治療期間はおよそ2〜3か月
「味覚障害」関連記事: