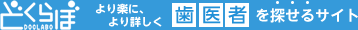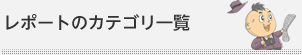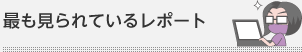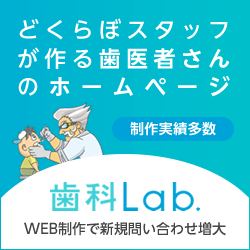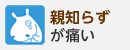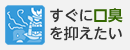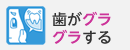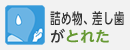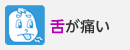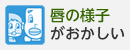頬杖と歯科の関係を教えて!
頬杖と歯科には深い関係があります。頬杖というのは、手の平を顎に置いて頭を支えるという動作ですが、このことが継続的に行われることにより、歯科に関わる様々な悪影響を引き起こします。その例として5つ挙げられます。
1.歯並びが内側に倒れる
手の平をほっぺの部分に当てて歯を内側に押すような形になってしまっている場合、歯に持続的に力が加わり続けます。人間の頭は成人の場合5キロくらいの重さがあると言われており、その力がかかり続けると歯が内側に倒れた狭い歯並びになってしまう恐れがあります。
2.顔が変形する
成長期に頬杖の癖があると顔がだんだんと歪んで成長してきます。例えば、決まった側でばかり頬杖をつく癖がある場合、顔がだんだん歪んで左右非対称になってきます。両方で頬杖をつく場合は、上の顎が出てしまう上顎前突になることがあります。
3.顎関節症を引き起こす
あごに持続的に頭の重さほどの力がかかり続けることで、顎関節を圧迫したり、咀嚼筋を過度に緊張させてしまいます。それが原因となり、あごの痛みや、口が開きづらくなったり、口の開け閉め時に雑音が鳴る顎関節症を引き起こします。また、顎関節症が元で頭痛や肩こり、首の痛み、腰痛のような体の様々な症状も引き起こしてきます。
4.歯を傷めてしまう
あごの下に手を置いて押し付けるように頬杖を行っている場合、上下の歯がグッとかみあった状態が続くことにより、歯に力がかかり続けます。そのため、歯の歯根膜を傷めて歯の痛みなどの症状を引き起こす可能性もあります。
5.口呼吸になってしまう
1で説明したように、歯が内側に倒れてくると、歯並びが狭くなってしまいます。そうすると、舌は歯並びの中に収まりにくく、沈下舌(舌が喉の方に落ち込んだ状態)となります。それにより、気道がふさがれる形となり、呼気量が十分に確保できなくなるため、口呼吸を引き起こします。口呼吸は歯並びや顔面の変形を引き起こしたり、口臭、虫歯、歯周病のリスクを高めたり、アレルギーや風邪などの感染症を起こしやすくするなど、さまざまな悪影響があります。
頬杖以外の歯並びに与える悪癖について
頬杖をしていると歯並びが悪くなってしまうことがある、ということは最初の項目で触れましたが、頬杖の他にも日常生活の中で無意識に行ってしまう、全身的な癖のことを態癖(たいへき)と呼んでいます。
頬杖以外の態癖には次のようなものがあります。
1.寝癖
うつ伏せ寝や、同じ側をいつも下にして寝る、などを続けていると、顔が左右非対称に歪んでしまったり、顎関節症、歯並びの異常が起こる原因となります。
2.悪い姿勢
姿勢が悪いと、かみ合わせやあごがずれてしまったり、顔が左右非対称に歪んでしまう原因になります。
3.片がみ
いつも同じ側でばかりかんでいると歯並びやあごの成長にも異変をきたします。テレビを見るために顔を横に向けて食べている場合などに片がみが起こりやすくなると言われています。
頬杖をついてしまう原因について
どうして頬杖をつくんですか?と聞かれてすぐに理由を答えられる人はあまりいないでしょう。
頬杖をつくときに多い状況
- ぼんやりしている時
- 何か考え事をしている時
- テレビを見ている時
- 勉強している時
頬杖をしてしまう心理的な理由
- 退屈している
- 不満がある
- ストレスや不安がある
- 緊張している
- 疲れている
というようなことが言われており、どちらかというとネガティブな感情がある時に多く出る傾向があるようです。
一人でいる時に頬杖をつく場合、頬杖で頭を支えることにより精神的に安心が得られたり、手で自分の顔やあごなどに触れていることで安心を得る自己密着心理が働いていると言われています。
それに対し、やる気のなさ、退屈さ、不満を表現している場合もあります。相手の前で頬杖をつくことによってネガティブな気持ちを無意識にアピールするような場合です。話している相手が頬杖をついていたらあまりいい気持ちがしませんよね。
また、完全に癖になってしまっている場合もあるようです。そのような場合には暇さえあれば頬杖をついてしまうので、状況は深刻になってきます。
頬杖をやめる方法を教えて!
このように、頬杖は心理的に精神を安定させるような側面もあると言えるでしょうが、顔面に強い力がかかり続けることはやはり悪影響の方が大きすぎます。
<成長途中のお子さんの頬杖には要注意>
とくに、成長期のお子さんにおいては、そのような異常な力がかかり続けることは、歯並びや骨格の形成に大きな影響を与えるため、できるだけ早く止めさせる必要があります。また、見た目的にも頬杖はだらしない、不真面目、やる気のないというような印象を他人に与えてしまうため、そういった意味でも早く治すのがお子さんのためでもあります。
成人やある程度大きくなったお子さんであれば、頬杖が体に悪いと分かればすぐにやめることが可能ですが、小さなお子さんの場合はなかなか止めさせるのに苦労するかもしれません。そんな時は無理やりやめさせようとしても別な悪い癖が出る可能性がありますから、お子さんの気持ちに寄り添って、不安や不満などの気持ちを取り除きつつ、「一緒に止めていこうね」という親の姿勢もとても大事だと言えるでしょう。
こどもの頬杖をやめさせる方法
1.とにかく見つけたら注意する
まず始めに、「頬杖が体に悪いものだ」というのを言い聞かせ、続けていたらどうなってしまうのか、ということをきちんと説明して理解してもらうことが最も重要です。その上で、頬杖をしているのを見つけたら、その度に注意し、すぐに止めさせるようにしましょう。癖になっているとなかなかやめるのは大変ですが、決して叱らず、根気強く注意し続けることが大事です。
2.何か夢中になることをさせる
本当に好きなことに夢中になっている時は頬杖もしなくなるものです。テレビばかり見させるのではなく、お子さんが夢中になれることを見つけてあげるのもいいですし、お父さん、お母さんが一緒になって遊んであげることで、お子さんも精神的に安心し、頬杖の癖が出にくくなることでしょう。
3.心理的な不安などを取り除いてあげる
頬杖はストレスや不満、不安、欲求不満や構って欲しい要求の表れの側面があります。お子さんと十分なスキンシップ、コミュニケーションを取ることで、心理的な不満を取り除いてあげることも改善につながります。
4.頬杖をしなかったらきちんと褒める
また、頬杖をしなかったらちゃんと褒めてあげることもモチベーションの向上につながります。
5.親自身も頬杖をしないようにする
子供は親のやることを真似るものです。親が頬杖をついていたらそれを真似てしまうことも当然あるでしょう。こどもにやめさせようとするならば、まずは親が徹底して頬杖をつかない、ということが大事です。
頬杖と歯科の関係について まとめ
頬杖や他の態癖への歯並び・骨格への影響は、すぐに目に見える訳ではなく、少しずつ年月をかけて現れてくるものです。そのため、成長期の段階で歯やあごに異常な力をかけることなく、かつ、左右バランスよく機能させることがとても大事になってきます。ひとたび「癖」になってしまうと、治すのがなかなか大変になってしまい、顔が大きく歪んでしまうことにもなりかねません。そしてその顔のゆがみを治す手段としてはあごの手術しかありません。そのようなことにならないためにも、異常な行動が見られたら親御さんが早めに修正をしてあげることが大切です。
「頬杖」関連記事:
乳歯の歯並びについて。気になる7つの質問に歯科医師がお答えします!