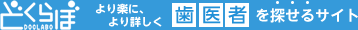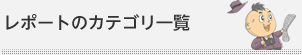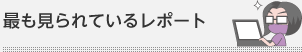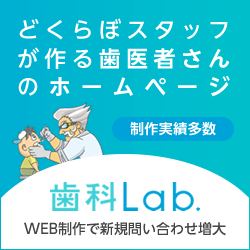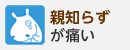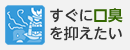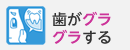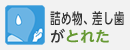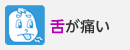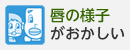不正咬合とはどのようなものですか?
「不正咬合」とは、一言で表すならば、「その人にとっては正常と判断することが出来ない、咬合(噛み合わせ)の状態」とまとめることが出来ます。
ここで気をつけたいのが、『その人にとっては正常と判断することが出来ない』という点です。細かな分類を使えば、しっかりと決まったルールによって「正常or不正常(正常ではない)」を区別することが出来るのですが、分類法も様々存在しますし、
ある人にとっての不正咬合も、他のある人にとっては不正と感じない(問題を感じていない)ケースも存在します。
<上顎前突を例にして解説>
不正咬合の一種に「上顎前突」というものがあります。上顎(上の顎)が、前突(前に飛び出している)しているというように解釈できる不正咬合の分類法なのですが、いわゆる「出っ歯」もこの上顎前突に関連するキーワードです。この出っ歯、程度がヒドすぎて食事に影響が出てしまう方もいれば、単に見た目が少し気になるだけ、という方もおられます。逆に、出っ歯を全く気にすることなく、むしろ自分の個性として魅力に思っている方もおられます。
<患者一人ひとりによって様々な捉え方が出来る>
このように、「不正咬合」という言葉を使う際は、「誰が、何を正常、不正ととらえるのか?」という点を考慮しなければなりません。患者様一人ひとりによって様々な捉え方がる。それが「不正咬合」なのです。とは言っても、「不正咬合とはどのようなものなのか?」という問いに対して明確な答えが存在しない訳ではございません。ここからは、歯科矯正の現場などで多く利用されている、「噛み合わせに不都合を感じて受診した患者様」に対して提示するための不正咬合の分類について列挙致します。
<分類法1>歯一つひとつの位置による不正咬合の分類
叢生(ソウセイ)
いわゆる「歯並びが悪い」と言われる状態を指します。一本の歯だけが少しズレているだけであったり、多くの歯が正常と呼ばれる位置からズレているために歯並び全体がチグハグにズレあっている状態のものまで、その程度は様々です。
捻転(ネンテン)
歯が縦の軸(歯の根っこの軸)を中心に、回転、つまり捩じれている状態を指します。
傾斜(ケイシャ)
歯が前後方向に傾いている状態をさします。前歯が前向きに傾いているものを唇側傾斜、後ろ向きに傾いているものを舌側傾斜と、専門的に区別することもございます。
<分類法2>上下の歯列弓(一連の歯並び)の水平的な(前後的な)関係性による不正咬合の分類
Angle1級
Angle1級と呼ばれるタイプの咬合状態(噛み合わせ)は、厳密には不正咬合とは呼ばない理想的な咬合状態です。ただ、不正咬合の治療を行なってゆく上で、重要な”目指すべき咬合状態”でありますので、矯正治療の現場などでは非常によく使われる言葉です。
Angle2級
Angle2級と呼ばれるタイプの咬合状態は、上の顎の歯列(歯並び全体)が、下のそれと比べて前方向に偏っている不正咬合のことを指します。先程触れた「上顎前突」と呼ばれる不正咬合も、このAngle2級に含まれます。
Angle3級
Angle3級と呼ばれるタイプの咬合状態は、Angle2級とは逆に、下の顎の歯列(歯並び全体)が、上の歯列と比べて前方向に偏って位置している不正咬合です。「下顎前突」と呼ばれることもあります。”下のあご(下顎)”が”前に出ている(前突)”というイメージを持って頂ければ分かり易いかと思います。いわゆる「受け口」といった噛み合わせの状態も、このAngle3級に含まれます。
<分類法3>上下の歯列弓(一連の歯並び)の垂直的な(上下的な)関係性による不正咬合の分類
過蓋咬合
過蓋咬合とは、上下の歯列が通常よりも深くかみ合っているタイプの不正咬合を指します。上の前歯が、下の前歯のほとんどを隠してしまっているイメージを持って頂ければ幸いです。
開口
開口とは、”口が開いている状態”、つまり、上の歯列と下の歯列の上下的な位置関係が、通常よりも離れているタイプの不正咬合を指します。奥歯を噛み合わせた状態であっても、上と下の前歯が離れ合っており、狭い隙間が空いてしまっている状態をイメージすると分かり易いです。いわゆる、「すきっ歯」と呼ばれるものも、開口というタイプの不正咬合に含まれます。
幼児の不正咬合はカラダにどんな悪影響を与えますか?
不正咬合がカラダに与える影響が様々存在します。特に幼児期は日々のカラダの変化(成長)が著しいため、不正咬合によって生まれる影響に関しても、注意深く捉えてゆく必要があります。幼児期の不正咬合を放置してしまった結果に生じる、代表的な悪影響について以下に述べてゆきます。
虫歯や歯周病のリスクが上がってしまう
歯並びが整っていない、つまり、不正咬合が存在すると、歯を磨く作業が複雑になってしまいます。つまり、歯が磨きにくくなってしまうのです。幼児期の歯(乳歯)は、成人のそれと比べて虫歯に対する抵抗が弱いとされています。ただでさえ歯を磨く習慣が固まっていない幼児ですので、不正咬合のせいで歯磨きが丁寧に行なわれないと、磨きの残しによって歯が不清潔な状態に保たれてしまいます。その結果生じやすくなるのは、もちろん虫歯ですね。虫歯の他にも、歯肉炎など歯周病の症状も、不正咬合を持つ幼児には現れやすいと言えます。
発音への影響
口の中はとても狭い空間であり、その環境の少しの変化が生活に大きな影響を及ぼすこととなります。その中でも「発音への影響」は、言語機能の発達段階にある幼児にとって、非常に重要なものとなります。歯並びの不具合によって、唇や舌の動きに微妙な ”動かしづらさ” が生まれると、それに関連して、発音の面でも ”しゃべりづらさ” が生じてしまうのです。不正咬合による発音障害は、それが原因で、幼児の性格にも影響を及ぼしてしまう可能性もあります。人と違った発音(しゃべり方)を気にしてしまって、しゃべることが苦手なままに成長してしまうケースも存在します。
顎の成長の偏り
幼児期の不正咬合は、歯が生えている “土台” である顎の発育にも影響を及ぼします。歯並びの悪さから、噛みにくい部位が存在した場合、自然とその部位の歯を使って食事をする機会は減ってゆくものです。例えば、右・左と上下の歯を分けて考えるとしましょう。歯並びの悪さが原因で、右半分で噛むことが難しい(噛みにくい)場合、食事をとる際に、逆側の左側ばかりで噛んでしまいがちになることは、皆さんも想像できるのではないでしょうか?
偏った部位(左右どちらか)の歯ばかりを使っていると、歯の土台である顎の発育に左右差が生じてしまいます。ただでさえ発育が盛んな幼児です。偏った噛み合わせを放置することによって、顎の形の左右のバランスが崩れてしまうケースも少なくありません。
不正咬合の原因は?
不正咬合の原因は、非常に多くの要素が組合わさっていると考えられています。ただ1つの原因だけで不正咬合が生じるケースは数少なく、不正咬合を持たれる一人一人の患者様に、それぞれ異なった組み合わせの原因が存在します。以下に、不正咬合の原因の一要素とされる、代表的のものを挙げてゆきます。
遺伝要素
歯並びというものは、顎の位置関係と深く関係しております。先に述べた、「Angle○級」といった不正咬合の分類も、上下の顎の位置関係を反映した分類法に含まれます。1つ1つの歯の位置が遺伝によって直接影響を受けることはないとされているのですが、歯の土台である顎の位置は遺伝によって強い影響を受けるとされています。がっちりとした骨格の親から、おなじような骨格の子が生まれるように、顎の位置関係のズレというものも、親から子へその特徴が遺伝することが多いという訳です。
幼児期の悪習慣
ここで言う悪習慣とは、
- 指しゃぶり
- 爪をよく噛む
- 唇をよく噛み込む等
幼児期に誰でも少なからずは見られるものを指します。先程から繰り返していますが、幼い子どもというのは、日々カラダの発育を遂げています。日々めまぐるしく変化する成長の過程で、これらの習慣の程度が大きい場合、上下の前歯が開いてしまったり(すきっ歯)、前歯が前に出過ぎてしまう(出っ歯)ケースが存在します。
虫歯
不正咬合の発現には、虫歯も大きく関係しています。例えば、虫歯を放置して抜歯をせざるを得ない状況になったとします。抜歯後にぽっかり空いたスペースをそのままにされてしまった場合、隣合う歯は、そのスペースに向けて少しずつ傾いてくることとなります。幼児であれば、抜歯をした後に永久歯(大人の歯)が生えてくるのですが、隣り合う歯の傾きによって、永久歯が生えて来るはずのスペースが足りなくなってしまうケースがあります。そうなると、十分なスペースを探すように、生えて来る永久歯は正常とは少しズレた位置から顔を出すことになります。1つの歯の位置のズレは、歯並び全体に大なり小なりの影響を及ぼします。幼児期の虫歯の放置が、その後の歯並び全体に悪影響を及ぼすこととなるのです。
治療が必要な不正咬合とは?
歯並び(咬合)というものは、冒頭で述べたように「正常or不正」を判断するのが非常に難しいものです。同じような歯並びでも、人によってその捉え方は様々です。治療が必要な不正咬合についても、その線引きが曖昧なのですが、以下に代表的なケースについてご説明致します。
見た目を改善するための治療を行なうケース
不正咬合の症状の中で、最も大きいともされるのが「見た目」への悪影響です。子どもから大人まで、人は少なからず他人の目を気にして生活してゆくものですが、歯並びの見た目に対する感じ方もひとそれぞれです。その不正咬合の見た目が、その人にとって「改善したい」と思うのであれば、どんなタイプの歯並びであっても、それは、”治療が必要な不正咬合” と呼べるでしょう。
骨格的なズレが著しいタイプの不正咬合
ここで言う骨格のズレとは、「上下の顎の位置関係のズレ」と言い換えることが出来ます。例えば、下の顎が極端に前に出過ぎてしまっている場合、見た目はもちろんのこと、「上手く噛めずに食事がとりずらい。」といった、生活に大きく支障が出てしまうケースがあります。毎日とる食事。そこに影響が出てしまうことは、生活全体に他の悪影響を生んでしまう可能性が大きくなります。このように、日常生活に無視できない影響が生じるタイプの不正咬合も、”治療が必要な不正咬合”と言えます。
治療をする場合はどんな治療法がありますか?
いざ不正咬合の治療を行なう場合、その治療内容が気になるところであると思いますが、不正咬合の種類自体が多種多様に及ぶため、当然その治療内容も様々です。基本的には、矯正歯科が不正咬合の治療を専門的に行なってゆくのですが、小児歯科や口腔外科も不正咬合治療と非常に関連性が深いと言えます。詳しい内容はそれぞれの口の中をみないことには判断できませんので、気になる不正咬合の症状がある場合は、最寄りの歯科医院などにてまず相談することが望ましいです。
不正咬合について まとめ
最後に不正咬合について重要な点をおさらいしておきましょう。
3つの分類方法と、治療の必要性
1、歯一つひとつの位置による分類
- 叢生
- 捻転
- 傾斜
2、上下の歯列弓の水平的な関係性による分類
- Angle1級
- Angle2級
- Angle3級
3、上下の歯列弓の垂直的な関係性による分類
- 過蓋咬合
- 開口
治療が必要な場合
- 見た目を改善させたい場合
- 骨格的なズレが著しい場合
いかがでしたか。我々が運営しております”どくらぼ”には、他にも皆様の大切な歯に関する情報が盛りだくさんです!是非他の記事にも目を通していただき、正しい知識を身に付けてくだされば幸いです。今後とも”どくらぼ”を宜しくお願い申し上げます。最後までご覧頂きましてありがとうございました。
歯並びや噛み合わせに関する他の記事: