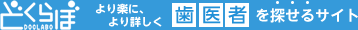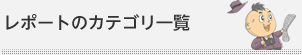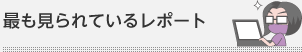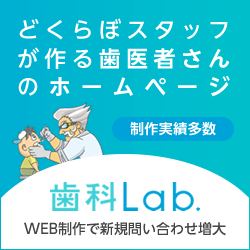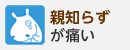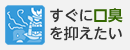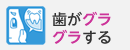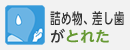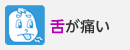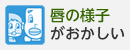皆さん、こんにちは! 歯科に関する情報を毎日更新している歯科メディア「どくらぼ」でございます!
本日のテーマは
実は奥が深い!知られざる総入れ歯の世界
をお届け致します。
アナタは総入れ歯について情報を集めているけれど、正直何がなんだかわからない。総入れ歯について詳しく知りたいのだけど、しっかりと解説してくれているページがない。とお困りではありませんか?
実際、どこのページを見ても総入れ歯に関して丁寧に解説しているページはなく、宣伝用に都合の良い総入れ歯を薦めているサイトが多いのが現状です。 ですので、本日は歯科衛生士さんの先生を行っている方から総入れ歯について徹底的に解説して頂きました。まずは、このページで総入れ歯についての正しい知識を身につけてから、どの総入れ歯を選択するかを考えてみてはいかがでしょうか?
そもそも、総入れ歯って何!?

総入れ歯とは、全ての歯が義歯(人工の歯)である入れ歯のことを指します。
多くの場合は「歯が1本もない人に使う入れ歯」のことを指して使われていますが、場合によっては歯があるけど見た目は総入れ歯という人もいます。見た目が同じ総入れ歯だとしても、歯があるかないかで使用感は大きく異なってきますので分けて考えてみたいと思います。
総入れ歯の特徴。上下で安定感に差が出る
総入れ歯を入れる際、上の入れ歯は上顎に吸着させることで支えますが、下の入れ歯は舌がある分吸着させる面積が少なく、安定感に欠ける傾向があります。顎の骨が少なければ尚更です。

総入れ歯の下に、歯を残しておくことで入れ歯が安定しやすくなる
歯を抜くと、その歯を支えていた顎の骨が痩せてしまい歯ぐきもそれにつられて高さを失いますので、骨を維持するためにあえて歯を抜かない場合もあります。残っている本数が極端に少なかったり、差し歯にするほど丈夫ではないけど残しておけば顎の骨を維持できると思われる場合にはその歯を短くし、蓋をして入れ歯の中に収まるようにします。そうすることで入れ歯が安定しやすくなるというメリットがあります。
歯を全部抜いてしまえば、虫歯にも歯周病にもならない!?
「歯を全部抜いてしまえば虫歯にも歯槽膿漏にもならないから全部抜いて総入れ歯にしてほしい」とおっしゃる方が時々います。確かに虫歯にも歯槽膿漏にもなりませんが、その後に入れる入れ歯は、その方が思うほど快適なものではないように思います。入れ歯はあくまでも義歯で、義手や義足と同じで不自由なく使える人の方が少ないと思うからです。総入れ歯を少しでも快適に使いたいと思えば、安定感はとても重要な課題ですので、歯があるかないかもまた重要なポイントとなるわけです。
残っている歯の状態で入れ歯の選択肢が変わってくる
残っている歯をどのように活用するかはケースバイケースになります。例えば残っている歯が前歯1本だという場合、その歯を支えにしてバネをかけ部分入れ歯にすることはできます。

しかし、その前歯に係る負担はとても大きく、長い目で見た場合にその歯の寿命を縮める結果となるかもしれません。また、バネがかかることや1本だけ別の歯が存在することで審美性が低下してしまうのであれば、残っている歯を短くして入れ歯の中に入れて保存するというのも選択肢の1つだと思います。
別の例としては、左右の奥歯が1本ずつ残っている場合。この場合は、その歯が比較的しっかりしているのなら、蓋をして総入れ歯の下に入れてしまうよりも、バネをかけ部分入れ歯の支えとして使うことで入れ歯を安定させることができるかもしれません。このように、どこの歯が何本、どのような状態で残っているのかでメリットやデメリット、つまりは治療の選択肢が変わってきます。
総入れ歯の種類

保険診療か非保険診療(自由診療)か
一言に「総入れ歯」と言っても、実は様々な種類があります。その中でも大きく分けると、保険の中で対応可能な“保険診療”
保険診療と比べると値段はかかってしまいますが、その分メリットが非常に多い “保険外診療(自由診療)”
この2つが総入れ歯の種類を考える時の大きな区別となります。
例保険診療で作製するか自費診療で作成するかどうかで使用できる材料やそれに伴う治療費は異なります。
保険診療で作る総入れ歯

保険診療で総入れ歯を作成する場合、「レジン」と呼ばれるプラスチックに似た材料で作製するのが一般的です。ピンク色のレジンを歯茎の代わりにし人工の歯を並べます。人工の歯は硬質レジンと呼ばれる硬めのレジンでできたものを使うのが主流となっていますが、希望すれば陶材(セラミックなど)でできた歯にすることも可能です。
入れ歯の歯は陶材(セラミック)がいい?硬質レジンがいい?
硬質レジンと陶材の違いはその固さです。陶材のほうが硬く、磨り減りや着色を起こしにくいというメリットがあります。しかし、衝撃には弱く、破折の可能性があることや噛みあわせた時にカチカチと音がしやすいことから今は硬質レジンが多く使われています。
スルフォンという素材

ピンク色の歯ぐきにあたる部分(床といいます)は保険診療ではレジンで作られることがほとんどですが、「スルフォン」という素材で作ることも可能です。
レジンはプラスチックに似た素材であまり強度がないので、噛んだ時の力に耐えられるようやや厚みを持たせて作られます。そのため、口の中が狭くなり喋りづらい、食べづらいと感じる人もいます。また、目には見えない細かい穴が空いているので吸水性があり、使用しているうちに茶渋などの色がついたり、臭いがついてしまうこともあります。
スルフォンはレジンに比べて熱に強く、比較的丈夫な素材です。また、吸水性が少ないのでレジンに比べて臭いがつきにくいという特徴もあります。スルフォン製の入れ歯にする場合、人工の歯もスルフォン製になりますので前述の硬質レジンより着色も気にならないと思います。治療費はレジンで作る一般的な入れ歯で10,000~15,000円程度(上下どちらか片方)、スルフォンですとプラス3,000円前後になるかと思います。
自費診療(自由診療)で作る総入れ歯
保険診療を離れ、自費で総入れ歯を作成することもできます。自費で作成するということは全額自己負担ということなので治療費は高額になることが予想されますが、それを上回るメリットがある場合、あえてそうすることもあるでしょう。
保険診療のデメリットは、厚みがあること
保険診療ではプラスチックに似た素材で作るため、ある程度厚さをもたせた作りにしないと噛む力に耐えられません。しかし、厚くすることで口の中が狭くなり、喋りにくい、食べにくいと感じる方もいます。また、プラスチックは熱を伝えにくいので大きく上顎を覆う総入れ歯の場合、食事の温度があまり感じられず美味しくないと感じる方もいるようです。
自費診療だと厚みを薄くでき、快適な総入れ歯を作ることが出来る
総入れ歯をなるべく薄く、快適にしたい場合、その素材を丈夫なものに変えることで解決することができます。例えば、上顎を覆う部分を金属にした「金属床義歯」というものです。

金属にするとプラスチックよりも強度があるので薄くしても割れにくくなります。 また、金属は熱の伝わりがいいので食事の温度もより感じやすくなりますし、プラスチックに比べて臭いがつきにくいのも特徴です。
ただし、金属アレルギーがある場合、使えない方もいますので注意が必要です。金属床義歯は使用する金属によって使い心地や費用が異なります。
金属床義歯の種類
【コバルトクロム】
例えば「コバルトクロム」「チタン」「ゴールド」がよく使われている素材ですが、1番歴史があるのはコバルトクロムです。熱を伝えやすく、薄くても壊れにくいのが特徴です。金額はこの3つの中では1番安く250,000円前後ほどです。
【チタン】
次に、近年増えてきているのがチタンです。チタンはアレルギーの心配が少なく、この中では一番軽いのが特徴です。ずっと口の中に入れておくものなので軽いものの方が違和感が少なく楽に感じるかもしれません。金額はコバルトクロムより少し高めの350,000円前後になります。
【ゴールド】
最後にゴールドですが、ゴールドの1番の特徴は生態親和性が高い、つまり体に馴染みやすいことだと思います。金属の中では柔らかく、成形もしやすいです。ただ、金額は500,000円ほどかかることもあるので上下で入れた場合、小さな軽自動車が1台買えるくらいの金額になることもあるかもしれません。
金属床のデメリット
ただし、いくら薄くて丈夫な金属床義歯でも、自分の歯茎の形が変わるかもしれない、何かの拍子で壊れてしまうかもしれない、など一生使える保証はありません。
金属床義歯はどれも、破損した場合は修理が難しいので場合によっては作り直しになるかもしれないことを念頭に置いておく必要があります。
食事を楽しみやすい、総入れ歯
食事を今まで通り楽しみたい場合、上顎部分が特殊合金で出来た「トルティッシュプレート」という入れ歯もあります。
金属部分が特殊加工されており、目に見えない40万個の穴が開いたメッシュ素材で出来ています。ですので水分を通し、食べ物や飲み物の温度や味も、他の入れ歯に比べて感じやすいのが特徴です。水分を通すので加齢や服薬の影響などによって口腔乾燥がある方にも適しています。
費用は300,000円前後ですが、今使っている入れ歯の上顎部分だけをメッシュ素材に替えることができる医院ではもう少し価格が抑えられるかもしれません。
歯が安定しやすく、違和感の少ない「テレスコープ義歯」
自分の歯が残っていれば顎の骨が維持しやすいことは前述したとおりですが、さらに安定させるために、残っている歯に蓋だけするのではなく柱として活用しようというのが「テレスコープ義歯」です。

残っている歯に「内冠」と呼ばれる柱状の被せ物を入れ、その上に入れ歯、もしくは入れ歯と一体化させた差し歯をかぶせます。入れ歯に芯が通ることになるので、歯ぐきに吸着させる従来の入れ歯に比べてしっかり安定するのがポイントです。
内冠と被せるものがぴったり合えば入れ歯はかなり安定してズレや違和感は軽減されますが、そのためには型取りから作成まで、歯科医師と歯科技工士の高い技術が求められます。費用は入れ歯本体が300,000円前後、加えて内冠が1本100,000円前後かかるかと思われます。
入れ歯を固定する装置が内蔵されている「アタッチメント義歯」

アタッチメント義歯はテレスコープ義歯と同じように残っている自分の歯を利用して入れ歯を支えます。アタッチメント義歯は残っている歯と、対になる入れ歯の両部分に小さな付属品を取り付け、仕掛けを作った入れ歯の総称です。
アタッチメント義歯にはいくつか種類がありますが総入れ歯に使うものの代表としては「マグネット義歯」があります。残っている歯と、それに対になる入れ歯の部分に磁石を埋め込みくっつけることで入れ歯を安定させることができます。アタッチメント義歯はその仕掛けによって金額が異なりますが1ヶ所おおよそ100,000円ほどになります。
自分の歯が一本もない時にはインプラントを使うという方法も

テレスコープ義歯もアタッチメント義歯も、自分の歯が残っていることが条件となりますが、自分の歯が1本もない場合でも(数本残っている自分の歯を助ける意味でも)インプラントというボルトのようなものを顎の骨に埋め込み、歯の代わりとする方法もあります。
入れ歯を安定させる意味ではとても有用な手段ですが、ボルトを埋め込んだ後も自分の歯と同様にメインテナンスしていく必要があります。また、ボルトを埋め込むために外科手術が必要になり、入れ歯の作成とは別に治療回数や期間がかかることと健康保険が適応にならないので治療費が高額になりやすいことはデメリットといえるかもしれません。
入れ歯を作っていく上で大切な“安定感”を生み出す「ソフトデンチャーとシリコンデンチャー」
入れ歯を使っていく上で安定感は大きなポイントですが、どんなに安定している入れ歯でも痛みが伴うようでは使用できません。顎の骨の形や量はもちろん、歯ぐきの厚さや感じ方は人それぞれです。ぴったり合う入れ歯を作成できたとしても、痛みが強く使用できないこともあります。
そんな場合は「ソフトデンチャー」や「シリコーンデンチャー」という入れ歯にすると楽になるかもしれません。

歯ぐきに接触する部分に柔らかい弾力のある素材を敷くことで、噛んだ時の痛みを軽減したり、フィット感を高めることができます。
特殊な素材のため、歯科医院での定期的な調整が必要で(基本的にはどの入れ歯にも言えることですが)自宅でのお手入れにもコツがいるのがデメリットといえるかもしれませんが弾力があるので力を入れて噛むことができます。価格は250,000円前後です。
軽い装着感が特徴の「フィンデンチャー」

特に軽い装着感を求める場合「フィンデンチャー」という入れ歯の端の部分が特殊な材料でできた入れ歯もあります。薄く軟らかい素材が歯ぐきにまとわりつくようにぴったりフィットするので浮き上がりやズレが軽減されます。
ただし、この素材も取り扱いに注意が必要で乱暴に扱うと破けてしまうこともありますし、半年に1度位のペースで張替えをする必要があります。価格はソフトデンチャーとおおよそ同じくらいと思われますが、フィン以外のベース部分を金属床にすると値段が上がることもあります。
総入れ歯を作る時に注意したいポイント

自分の中で何を重視したいのかを明確にすること
残念なのですが、自分の歯以上に完璧な総入れ歯は存在しません。ですので、総入れ歯を作成する際は、「自分の中で何が大切なのか」を明確にすることが重要です。
・食事を楽しみたい
・違和感なく装着したい
・見た目を良くしたい
・費用は出来る限り安くしたい
など自分の中で大切にしたいことを明確にし、優先順位をつけて選んでみてください。
歯科医院側としっかりと連携をすること
自分の中での価値観が固まったら、今度はそれを歯科医院側にしっかりと理解してもらいましょう。どんなに歯科医師や歯科技工士の腕が良くても、1度で完璧な入れ歯が仕上がることは少ないです。
出来上がった後も調整が必要になるうえに、定期的に点検をして、必要があれば修理や調整を繰り返すことで自分に合う入れ歯に仕上がっていくと思うので、諦めてしまわずに調整に通うことも必要なことだと思います。
良い総入れ歯を作成してくれる歯科医院の見分け方
自分の都合ばかりを押し付ける歯医者さんは選ばない方がいいいい入れ歯を作ってくれる歯医者さんも同様で、ぱっと見での見分け方はありません。しかし、患者さんの話を聞かず、その歯科医院の都合の良い入れ歯ばかりを勧めてくる歯医者さんはオススメしません。ちょっとおかしいなと感じたら他の歯科医院の話も聞いてみたほうが良いです。
アナタの望むこと、要望をしっかりと聞いてくれ、互いに協力しあって良い入れ歯をつくろうとしてくれる歯科医院を選ぶことが大切です。
以上で、総入れ歯の解説を終わります。アナタにとって最適な総入れ歯ができるお力添えになれましたでしょうか。
非常に長いものを最後までお付き合い頂き、感謝致します。どくらぼ編集部がお送り致しました。ありがとうございました。また是非お会い致しましょう!